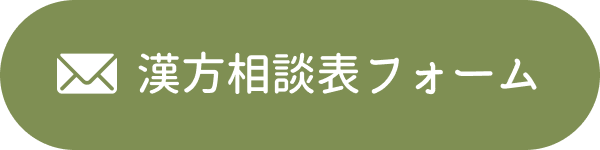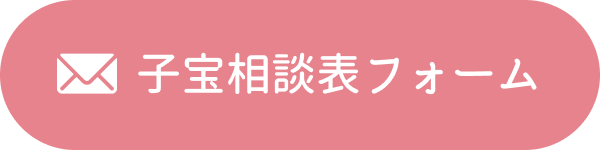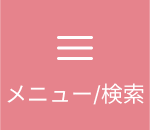卵巣疾患への漢方療法の紹介…卵巣嚢腫、チョコレート嚢腫、多嚢胞性卵巣症候の漢方、漢方薬
昨日の23日(祝日)は、当店では中医師の何(ふー)先生をお迎えしまして、漢方相談会を行いました。 大変と好評のうちに終わることができまして、ほっとしているところです。漢方相談会で多かった内容は、卵巣のトラブルのことでした。
12日~20日まで中国出張だった上海出身の何先生がおっしゃるには、中国では子宮内膜症や卵巣発育不良(先天性)の疾患が多く見受けられるそうです。 日本では、卵巣疾患が多いようだとおっしゃっていました。
卵巣嚢腫など卵巣疾患の要因としましては、中医学的に考察すれば、足元を冷やすような生活や冷え性と関連があるらしいです。

<湧泉のツボ>
足の裏のツボには、湧泉があります。湧泉は、ちょうど土踏まずのところにあり腎の経絡のツボです。
はだしなどで足元を冷やしていると、湧泉から寒邪(かんじゃ)という寒さの邪気が入ります。
湧泉を入り口とした腎の経絡のは、卵巣と結びついています。
私たちはふだん何気なしに、冷え性で足元が冷えるとしか認識しませんが、上記の理由により「卵巣が冷える」こととなります。
「卵巣が冷えること」は、たとえて言うと川と同じで氷のようになりますから、血行不良、血液循環が悪くなり、瘀血(おけつ)を招きます。
卵巣の瘀血(おけつ)は、すなわち卵巣のトラブルとなり、「炎症」や「腫れ」を引き起こします。
これが卵巣嚢腫やチョコレート嚢胞、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)などの原因でもあるそうです。
もう一度まとめますと、 足元が冷える→湧泉から寒邪が侵入→卵巣の冷え→淤血(おけつ)→炎症と腫れ→卵巣嚢腫 となります。
キーワードは、①冷え ②淤血 ③卵巣のトラブル(炎症と腫れ) です。
中国漢方の対策としては、「ピクノジェノール配合の血行を良くする漢方薬」や「チャガ」などが効果的です。
「血行を良くする漢方薬」は、血液循環を良くして、冷え性と腫れ(炎症)に効きます。
「①冷え ②瘀血 ③卵巣のトラブル(炎症と腫れ)」すべてに作用があるので、おススメだそうです。
何先生は、さらに話を続けます。
日本人の小さい頃からの生活習慣も関係しているでしょう。
たとえば保育園で、どんなに寒くても裸足(はだし)で一日過ごさせることは、体が丈夫な子や丈夫で無い子と体質に差があるのですから、良くないことです。
(当店のスタッフも、昔から保育園や小学校などで、裸足(はだし)を奨励していることにやはり疑問を持っていたそうです)
中国では、足が冷えることは女性に一番と良くないと考えています。
ひどいと関節炎などの原因にもなります。
とくに生理のときには、足元や体は冷やさないようにします。
女子高生などのミニスカートは、生理のときにも足元を冷やしてしまいます。
将来の卵巣や不妊症の病気をつくることにも、繋がりかねません。 (実際に、当店でも「冷やさないようにしてください、とくに生理中は気をつけてください」とおススメすることがありますが、生理痛が生活習慣を変えただけでも楽になる人がいらっしゃいます。)
基礎体温表では、低温期に炎症や腫れの影響が現れます。
たとえば基礎体温で低温期がギザギザと波が激しかったり、生理になっても体温が下がらないなどです。 そのような状態は、何か卵巣の炎症や腫れなどのトラブルや、卵巣の働きが悪くなっていると考えます。
たとえば、排卵期が長いことは、①卵巣の問題 ②卵管の問題 などと検討します。
そのほかの生活習慣では、生理が始まる1週間前は夜更かしはダメです。
夜更かしは、生理の量が多くなります。 とくに2日目に経血量が多くなり、塊も多くでやすいです。
子宮筋腫がある人は、生理が来る1週間前は夜更かしはしないほうがいいでしょう。 11時前には寝ることが大切です。
夜の11~2時には、女性ホルモンがでますので夜更かしがあると難しいです。
などど、ためになる素晴らしい講義を受けました。
山形は、東京よりも生活習慣が良いそうです。 東京では夜更かしする人が多くて、それでは大変です。。 とおっしゃっていました。
今回の話が参考になりましたら幸いです。

足の冷えから卵巣のトラブルになるかも
薬剤師、認定不妊カウンセラー 土屋幸太郎
こちらの卵巣嚢腫に関するブログもご覧ください。
関連ブログはこちらになります。参考になりましたら、幸いです。
漢方相談表と子宝相談表はこちらです。
公式LINEもご予約や連絡や体調の変化などお気軽にご利用ください。便利です。